新発田市の焼峰山へ
2022年の9月21日。
台風14号が通り過ぎようとしている。
通り過ぎる前は、9月も終盤だというのに、気温が30度近くあり、とても蒸し暑かった。
予報を見ると、台風が過ぎた後の気温は、一気に20度ぐらいに下るようだ。
山を登るのに丁度よさそうな気温だ。
以前、角田山灯台コースを登った時、気温が高かったのと、本当に久しぶりの運動だったので、すっかりくたびれてしまった。

足の痛みが何日経っても消えず、段差の上り下りが辛かった。
二回目の山登りをしたいと思い、角田山と同じか、もう少しレベルの高いところで、どこか良さそうな所はないかと探していた。
そこで目をつけたのが焼峰山だった。
焼峰山は、新発田市の内の倉湖の近く、滝谷にある山だ。
新潟県のホームページに載っている、新潟 山のグレーディングによれば、3Bというグレードらしい。
新潟県の山の中では、ちょうど真ん中ぐらいのレベルのようだ。
途中にちょっとした鎖場や、崖際を通るようなところもあるようだ。
新潟百名山や分県登山ガイドなども見てみると、往復5~6時間ほどで登れるらしい。
登る予定の日は、昼に会議があるので、朝の4時ごろに登り始めれば仕事に間に合うだろう。
焼峰山の登山口近くにある駐車場へ
目覚ましをかけていた時刻よりも早く起きてしまった。
今は夜中の2:00ごろだ。
カヤックにしても釣りにしても、当日は億劫になって行こうかどうか迷うのだが、今回は体が勝手に動いた。
前回の角田山では、山頂からの見晴らしが良くなく、不完全燃焼だったのだ。
(向陽台から良い景色が見られるのを知らなかった)
焼峰山で山頂からの景色を見てみたい。
新発田市街から車を走らせ、内の倉湖の先、滝谷集落へと向かう。
加治川治水ダムへと向かう道を左折し、滝谷集落を通る。
登山口は、集落奥の林道をしばらく進んだところにある。
道はよく整備されており、焼峰山への看板もあるので、迷わずに着けた。
林道を進んでいくと、登山口の看板が見えてくる。
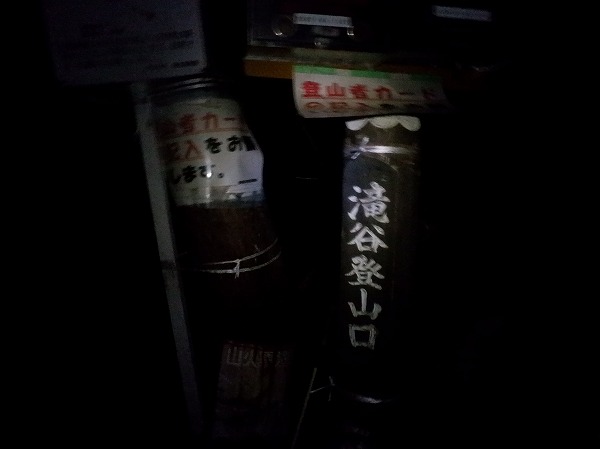
今は朝の3時半なので、真っ暗だ。
これは帰りに撮った登山口の写真だ。

右奥の道を進むと駐車場がある。

駐車場は、車が5~6台は停められるだろう。

右の道は、来た時の道だ。
林道の更に奥には、もう一つ駐車場があるらしい。
山登りの開始
準備をし、駐車場から徒歩で登山口を目指す。
ヘッドランプの明かりだけが頼りだ。
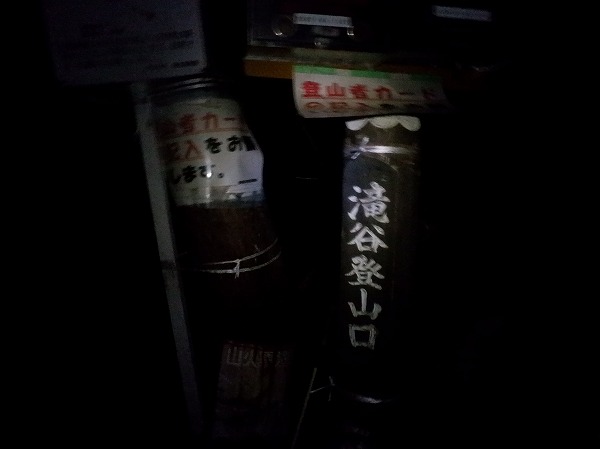
標識の左手にある道から、焼峰山を登り始める。

最初は林道のような雰囲気の道からスタート。
緩やかな勾配の道が続く。
辺りは真っ暗で何も見えない。
ヘッドランプの明かりだけで進むが、一昔前に流行ったフリーホラーゲームの世界にでも迷い込んだ気分になる。
後ろから何かが追いかけてくることを想像し、帰りたくなってくる。
登山やカヤックの前日は、気合を入れるために、つい重たいものを食べてしまう。
今日もだいぶ胃がきつい。
登山道は、下草がきれいに刈られており、とても歩きやすい。
ヘッドランプの明かりだけで進んだが、迷いそうな道もない。
登山道全体が良く手入れされていた。
越えるのが大変な場所は、鎖やロープが垂らされていたり、土嚢で歩きやすくなっている。
整備してくれた方に頭が上がらない。
途中、勾配のきついところがいくつかあり、そういった場所は石だらけだったり、粘土質の土が露出している。
前日の台風の雨で地面が濡れており、滑りやすくなっていた。
ようやく日が昇って来たようだ。

ヘッドランプの明かり無しでも十分進めるようになった。

しばらく林道を歩き続け、開けた場所に出た。

ここはうぐいす平という場所のはずだ。
うぐいす平で小休憩
新潟100名山という本によれば、焼峰山登山口からうぐいす平までは、約一時間の道のり。
時計で確認すると、たしかに焼峰山に入ってから一時間ほど経っている。
2つベンチがあり、奥のベンチからは遠くの山が眺望できる。


後で調べると、あの山は俎倉山という山らしい。

焼峰山と俎倉山、そして蒜場山の3山は、内の倉湖や加治川ダム周辺に位置している。
いずれ俎倉山や蒜場山も登ってみたい。
ベンチに小さいきのこ?が生えていた。

きのこの生えていないところに座らせてもらう。
しばらく休憩。
うぐいす平から、次のチェックポイントである清水釜まで、また一時間ほどかかるらしい。
そろそろ歩きはじめよう。

見晴らしの良い鎖場
うぐいす平を越えると、登山道の雰囲気が一変する。

トラロープや、鎖に捕まりながら進む場所がいくつか出てくる。
視界も開け、周囲の山々が見え始める。

途中、木の棒が土嚢で固定されていた。

おそらく、雨が降ったときに水はけを良くするために設えられたのだろう。
あれは何山だろうか。

周りの山々が目に入ってくるので、景色を楽しみながら登ることができる。
このような岩場の登りが何箇所もある。

今回の登山では、杖を持ってきていた。
登るときも下りるときも、杖は色々な場所で活躍してくれた。
急斜面を通るときは三点支持が基本だが、杖があると、手の届かない窪みなどに杖を差しながら進むことができる。
美しい山々の稜線。

山頂からはどのような景色が見られるのだろうか。
鎖の垂れた岩場を登る。

見た目ほど勾配はきつくなく、足がかりも適度にあるので、鎖をあてにしなくても苦労せずに登れた。
かなり高度が上がってきた。
遠くに平地が見える。

新発田方面だろう。
山の一部に光が射していた。

山々の深い谷間も見える。

この辺りはとても見晴らしが良い。
日が昇り始めている。

暖かくなるまでには焼峰山の山頂に着きたいものだ。
紅葉が始まりかけている。

山肌が削れて岩がむき出しになっている。
ああいうのをスラブというのだろうか。
周りの木々が背の低い灌木類になり、周囲の景色が良く見えるようになった。

景色を見ながら休み休み登っていく。

ところで、歩き始めて少ししてから鼻水が止まらない。
鼻をかむために、何度も立ち止まる。
角田山に登った時も鼻水が止まらなくなった。
ラーメンなど温かいものを食べた時も鼻水が出てくる。
こういうのを寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)というらしい。
登山への慣れで克服できるのだろうか。
尾根道を行く
尾根道を進んでいく。

万葉集4164番の、大伴家持の歌に「あしひきの 八峰踏み越え」という一節が出てくる。
尾根を進んでいるとこの歌を思い出し、勇壮な気分になってくる。
右を見ると山頂らしきものが見える。

あれが山頂だろうか。
それとも焼峰の頭だろうか。
いずれにしても、まだ距離がある。

こういう場所を歩いていると、昔NINTENDO64でプレイしたマリオ64に出てくるような、箱庭のステージを歩いているような気分になる。
見晴らしも良く、歩くのが楽しい。
相変わらず良い景色だ。

気が付けば、周りの山々の山頂と同じぐらいの高さまで来た。
手前が山頂だろうか。

それとも修蔵の峰か。
危ない鎖場
焼峰山登山道で、一番危険な箇所がここだった。

ロープを伝いながら斜面を横切っていく。

右下を見るとこのようになっており、転げ落ちたら一巻の終わりだ。

足場自体はしっかりしており、足がかりにできる場所も多い。
ロープにつかまりながら、ゆっくり三点支持で進めば難なく抜けられる。

歪んだ松。

雪の重みでこうなったのだろう。
灌木地帯を越えると、また背の高い木々が周りを覆い始めた。

粘土質や岩の斜面が続く。

落ち葉が溜まっているところは、岩のくぼみなので、そこを足場にすると良いことが分かった。

何やら看板を見つけた。ここが清水釜に違いない。

清水釜に到着
標高880m地点の、清水釜という看板が出ている。

青いパイプから水がちょろちょろと出ている。

飲んでみたが、冷たくておいしい水だった。
新潟百名山によれば、
登山口→清水釜まで2時間。
清水釜→次の修蔵峰までは30分ほどらしい。
そして、修蔵峰→焼峰山頂も30分ほど。
今の所、参考ペースとだいたい同じ時間で登って来られている。
山頂まであと少し。
ここまでで結構疲れがたまっているが、体に鞭を打ちながら歩を進める。
ここから山頂までの道は、山腹に沿って回っていくような道と、急登の連続だ。


ふと見ると、キノコが多く出ている。

白いキノコは毒キノコのイメージ。

登りを繰り返し、また視界が開け始める、、、

ようやく修蔵峰に着いた。

修蔵峰に到着
修蔵峰とは変わった名前だが、新潟100名山によれば、登山中に亡くなった本田修蔵氏を偲んで名付けられた名前だそうだ。
修蔵峰の慰霊碑。

慰霊碑に手を合わせ、しばらく休憩する。

周囲の山々が美しい。
山頂まであともう少しのはず。

先を見ると、また森の中を突っ切りながら、登りを繰り返すことになりそうだ、、、
さあ行こう。


木の根や幹を越えながら進む。

途中、一足で越えられないような、太い幹を越える場所もあった。
登りがひたすら続く。

辛い。
あとどのくらい登ればゴールなのだろうか。

ここが山頂か、、、

いや、まだ登りは続く、、、

雪の重みで木の幹が裂けたようだ。

道に猿の糞が落ちている。
黒っぽい糞だ。
急な坂を、ほうほうの態で越える。

上を見上げると、、、

急に視界が開けた!!



やっと焼峰山の山頂に出た、、、
焼峰山の山頂に到着
焼峰山山頂の標識。



山登り前に買っていた、キャラメルミルクコーヒーが胃に染みわたる。
本当に美味しい。
眼下には新発田の街並みが一望できる。


内の倉湖もよく見えている。

こちらは、焼峰の頭へと続く尾根道。

標識のところにザックを置き、焼峰の頭方面へと向かってみる。

これから紅葉の良い時期になるだろう。


尾根道を少し進み、左手を見ると二王子岳が見える。

奥の小さい山は櫛形山脈だろう。
日本一小さい山脈として知られており、地域に親しまれている山だ。
今度登りに行きたい。
二王子岳が存在感を放っている。

新潟市から、バイパスを通って新発田に来ると、二王子岳がよく見える。
それを正面とすると、今はだいたい側面の方から二王子岳を見ている形になる。
二本の大滝が見える。
滝をズーム

二王子岳の裾が広がっている。

右手には飯豊の山々が。

山々の名前は分からない。
さらに右を見渡す。

こちら側には俎倉山や蒜場山があるはずだ。


朝日に光るクモの巣。

焼峰の頭にたどり着くには、さらにここを登らなければいけないようだ。

体力的にも時間的にも厳しいので、引き返すことにした。
何かの実が成っている。

焼峰山山頂に戻ってきた。

初めて山頂らしい山頂に立ったので、喜びも一入だ。
パノラマで何枚か写真を撮ってみた。



さて、昼に会議があるので、余裕をもって下山したい。
もっと山頂でゆっくりしたいが、そろそろ引き返そう。
ここが登ってきた道。

ここまでの辛い行程を思い出す。
引き返そう。

焼峰山を下山
焼峰山を登る際、幾たびも急坂を越えてきた。
そうなると帰りが怖い。
幸い、険しい勾配の道には土嚢が積まれており、足掛かりにしやすくなっている。

登山道を整備してくれた人たちに、何度も感謝した。

何度も急勾配の道を下る。
その度に杖が大活躍だった。
崖際の斜面に戻ってきた。

実際の斜度はこのぐらい。

鎖場を降りる。

登りはスイスイ行けたが、下りは結構大変だった。
下りるときは、斜面の方を向く形で下りていくのがポイントのようだ。
仰向けだと体が安定しない。
筋力不足のためか、足が震え始める。
山を下る時、ちょっとした段差を飛び降りたりするが、そのときに靴がしっかり足に固定されていないと、靴ずれして痛くなってしまう。
今回は両足の外側、小指の辺りが痛くなった。
ようやくうぐいす平だ。

長めに休憩をとる。
下りはハイペースで歩いてしまうが、そうすると足に大きな負担がかかる。
ゆっくり動くことを意識しなければならない。
うぐいす平を後にする。

登山口までは、まだ30分以上かかる。
苔の生えている石は滑りやすいので注意が必要。



あともう少し。
自然と足が早くなる。

ようやく林道が見えた、、、

いや~ここまで大変だった。

山頂までの往復で、丁度6時間ぐらいだった。
駐車場に戻り、着替えて車を走らせた。
今回消費した500mlペットボトルは1本半だった。
登りで一本、下りで半分のペースだ。
下りはもう少しゆっくりと、水分補給をしながら下ったほうが良かったかもしれない。
今回は新発田の焼峰山を登ったが、前回の角田山灯台コースに比べるとかなり楽に感じた。
角田山に登った時は休日で、元々人出の多い山だったこともあり、結構な登山者がいた。
登っているときに下りの人とすれ違うと、下りの人が道を譲ってくれた時、急いで登らなければいけない気分になってしまう。
他の登山者に道を譲ったり、譲られたりしていると、ペースが乱れて結構きつい。
今回は平日だったため、登山者が全くおらず、完全に自分のペースで登ることができた。
また、持ってきた杖もかなり役に立った。
歩くときは荷重が腕にも分散されるし、疲れた時、杖に寄りかかって休むことができる。
焼峰山を下る際も、足を踏み出す付近に杖をつき、バランスを取りながら危なげなく降りることができた。
先述のように、全く登山者がいない中での登山だったので、ゆっくりと自分のペースで登ることができた。
周囲を見渡すゆとりもあり、楽しい登山だった。
角田山のときと比べ、筋肉痛もそれほどひどくない。
山に登れば登るほど体力が付いてくる感じがする。
これから登山には良い季節だ。いろいろな山に登りたい。
